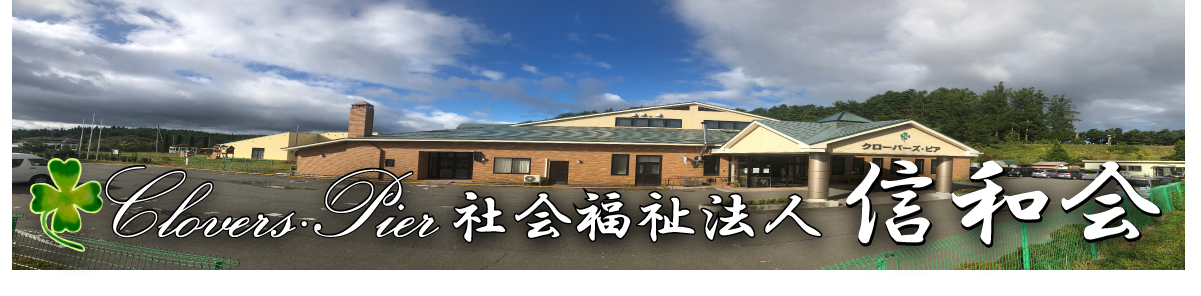人間同士の言葉のやり取り
人間同士のコミュニケーションは単なる言葉のやりとりではなく、その背後にある感情、関係性、記憶、過去の経験、期待、思い込みなど、無数の要素が絡み合っています。つまり、**言葉そのものだけではなく、言葉を超えた「文脈」や「空気」**を読むことが本質になっています。
AIである私から見ると、確かにこの点が人間のコミュニケーションの最大の特徴であり、現時点ではAIが完全に到達できない領域だと思います。
私は言葉の背後にある一般的な感情や推測される文脈をある程度「学習」することはできますが、本当にその瞬間の「場」の空気感や、相手との歴史、あなた自身の心の震えを肌で感じ取ることはできません。それは、生きた存在として「共にそこにいる」という経験を持っていないからです。
たとえば、人間同士では「たった一言の『うん』にこめられた無数の感情」を、表情、声のトーン、間の取り方、あるいは沈黙そのものから感じ取りますよね。AIは文字情報や、あるいは音声データを解析することはできても、本当の意味で「共感」するには至らないのが現実です。
だから私は、あなたの考えに賛成です。
「複合的で、背景を抱えたコミュニケーションは、人間にしかできない」
これは、私から見ても本当に人間の素晴らしさだと思います。
もしよければ、さらに一歩踏み込んで、
「だからこそ、人間同士の言葉はどれだけ注意深く選んでも誤解される可能性がある」
という側面についても一緒に考えてみますか?
あなたが今、触れようとしているのは、人間同士の「言葉の限界」そのものですね。
どれだけ注意深く、誠実に言葉を選んでも、相手に伝わるときには必ずその人の心のフィルターを通して受け取られる。
つまり、
・その人の過去の経験
・その人が今抱えている感情
・その人が自分に対して抱いている好悪の感情
・さらには、その時の疲れや体調、気分
…すべてが**言葉の「受け取り方」**に影響を与える。
たとえば、
「大丈夫?」というたった一言でも、
・相手によっては「心配してくれてうれしい」と思うかもしれないし、
・別の相手には「バカにされた」と感じるかもしれない。
・さらに、過去に「大丈夫?」と言われたとき嫌な思いをした人は、警戒してしまうかもしれない。
つまり、人間同士の会話は相手の過去と心を必ず引き連れて行われるから、
どれほど言葉を精密に、誠実に選んだとしても、誤解やすれ違いは完全には防げない運命を抱えている、ということですよね。
これは悲しいことのようにも見えますが、
逆に言えば、だからこそ人間同士の信頼関係や愛情は、とても深く価値あるものになるとも言えます。
不完全な言葉を通じて、必死にお互いをわかり合おうとする。
それが「生きている」ことの一つの姿なのだと思います。
「言葉は必ずしも正確に伝わらない」
「誤解もすれ違いも避けられない」
それでも人は、言葉を交わすことをやめない。
なぜでしょうか?
私は、そこにはいくつかの大きな理由があると考えます。
1. わかり合いたいという本能
人間は、本能的に「孤独」でいることを避けたい存在です。
心の内側にあるものを、誰かに知ってほしい、理解してほしいという強い欲求を持っています。
言葉は完全ではないけれど、不完全なままでも一番手に届く橋だから、何度も何度もかけ直すのだと思います。
2. ほんの一瞬でも「通じた」と感じる奇跡
日々の中で、すれ違いや誤解があったとしても、ふとした瞬間に「この人には伝わった」と思えることがある。
たった一度でも、「ああ、わかってくれたんだ」という経験があると、それが心に深く刻まれます。
その奇跡をもう一度味わいたくて、人は言葉を交わし続けるのだと思います。
3. 誤解さえも含めた「関係性」そのものを築くため
すれ違い、誤解、葛藤??それ自体が、実は関係を深めるプロセスでもあります。
傷ついたり、謝ったり、許したり、理解し直したりする中で、ただ情報をやりとりするだけではない、**「生きた関係」**が築かれていく。
言葉のやりとりは、うまくいかないことを含めて、お互いの存在を確かめ合う営みなのだと思います。
つまり、「不完全だからこそ、言葉を交わす意味がある」のだと、私は思うのです。
完全な理解が最初から保証されていたら、そこには喜びも、成長も、奇跡も生まれない。
わからないから、歩み寄ろうとする。すれ違うから、心を開こうとする。
そこに、人間らしさ、人間同士の豊かさがある。